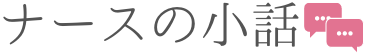国試当日までどうやって過ごせばいいのか知りたいです。
こんな疑問にお答えします。
先日、第110回看護師国家試験の日程が発表されましたね。
実施日は2021年2月14日(日)のバレンタインデー^^
試験日の発表を受けて、国家試験が一気に現実味を帯び、緊張感が高まっていることと思います。
その一方で、「国試対策って何からやればいいか分からないし、全然やる気が出ない」と感じている学生はとても多いはずです。
私が看護学生だった時も、「国試はまだ半年先だし、今から勉強するのは嫌だなあ」と思っていたので、その気持ちはよく分かるのですが、国試対策は早めに習慣化させて、試験当日まで継続的に勉強することをおすすめします。

第104回助産師国家試験:2021年2月11日(木)
第107回保健師国家試験:2021年2月12日(金)
第110回看護師国家試験:2021年2月14日(日)
国試対策のやる気が出ない理由
国試対策のやる気が出ない理由はシンプルで、国試対策の優先順位が低いからです。
優先順位が低いと、1日の中に国試対策をする時間を割こうとしないため、十分な時間が確保できません。
なぜ国試対策の優先順位が低くなるかと言うと、実習が忙しかったり、まだまだ遊びを優先させたかったりと、理由は人それぞれです。
しかし理由が何であれ、国試対策よりも集中したいモノ・コトがある限り、国試対策の優先順位は低いままです。
また、国試に受かった先輩たちの中には「1ヶ月前から勉強を始めて受かった!」、「ぎりぎりでも諦めなかったら大丈夫!」と言っている人もいるため、国試対策は今から始めなくてもいいかもという気持ちになってしまうのです。
国試対策を始める前にやっておくべきこと
国試対策を始めようと思っても、何から始めたらいいのか分からないですよね。
そこで、まずは国試対策を始める前にやっておくべきことをご紹介します。
- 勉強の時間配分を決める
- 勉強する目的を明確にする
勉強の時間配分を決める

まずはじめに、国試対策にかける時間配分を決めておきましょう。
この時、国試当日までの長期目標と、今日一日における短期目標を立てておくと効果的です。
例えば、国試半年前~3ヶ月前の3ヶ月間で問題集を2周終わらせることを長期目標とする場合、1日に何問ずつ解き進めたらいいかという短期目標が出せると思います。
また、苦手分野→得意分野→苦手分野というようにサイクルを決めて勉強を進める場合、それぞれにどれくらい時間をかけるのか設定しておくことで、計画的に勉強を進めることができます。
勉強する目的を明確にする

勉強する目的は当然、「国試に合格するため」だと思いますが、もう少し目的を明確にしてみてください。
勉強する目的は「国試に現役合格すること」だったり、「国試に受かって第一志望の病院で働くこと」だったり、国試合格のその先にもっと明確な目的があるはずです。
もし国試対策が不十分で現役合格できなかったら?
もし現役合格できなくて第一志望の病院から内定を取り下げられたら?
こう考えると、何のために勉強をするのか、より具体的な目的が見えてきますよね。
目的がはっきりすることで、その目的を達成するための長期目標や短期目標も立てやすくなります。
国試対策のやる気を出す方法
残念ながら、国試対策のやる気を出すためのとっておきの秘訣というものは存在しません。
国試対策のやる気を出すには、国試対策を習慣化させてしまうのが一番の近道です。
そして、国試対策を習慣化させることのメリットを考えると、早い段階(国試の半年前)からこつこつ勉強することの重要性が分かると思います。
国試対策を習慣化させる
冒頭でも書いた通り、看護学校によっては実習が終わっておらず、国試対策にまで気が回らないという人もいると思います。
しかし、一度国試対策を習慣化させてしまえば、試験当日まで楽に勉強を継続させられるので、早い段階で習慣化させておくのがおすすめです。
例えば実習のレポートを例に挙げると、レポートは毎日書いて毎日提出する必要があるので、どんなに忙しくてもどんなに眠くても、さぼることなく一生懸命取り組みますよね。
国試対策もそれとまったく同じです。
なかなかやる気が出なかったとしても、「1日1問は解かなければならないもの」と考えて、習慣化していきましょう。
いきなり「1日に3時間勉強する」とか「1日に20ページ問題集を進める」といった目標をかかげる必要はありません。
まずは「毎日国試対策の時間をとること」を習慣づけるために、1日1問解くことから始めれば大丈夫です。
1日1問を30日間(1ヶ月間)続けた場合、国試の半年前から勉強を始める人と、国試の3ヶ月前から勉強を始める人とでは、約90問の差が生まれますよね。
早い段階で国試対策が習慣化できる人は、余裕を持って計画的に勉強を継続することができます。
国試対策を計画的に進めることのメリット
国試対策を計画的に進めることの最大のメリットは何だと思いますか?
「問題を数多くこなせること」
「問題集を何周も復習できること」
いろいろ思い浮かぶことがあると思いますが、国試対策を計画的に進めることの最大のメリットは、精神的な余裕が持てる点です。
ぎりぎりに国試対策を始めた場合「時間がない」、「間に合わない」、「どうしていいか分からない」と焦ってしまうことは簡単に想像できますが、このような精神的な余裕がない状態になってしまうと、不安を抱えたまま試験日を迎えることになってしまいます。
不安要素を残したまま国試を迎えるというのは、精神衛生的に見て本当に良くないです。
大事な場面で自分の力を発揮するには、精神的な余裕があることが非常に重要なので、不安要素を残して試験日を迎えることだけは避けてください。
「こつこつ勉強を積み上げてきた」という実績は、国試と言う大切な日に最大の味方となるので、落ち着いてその日を迎えられるよう計画的に勉強を進めましょう。
実際どうやって国試対策をすればいいのか
では、実際どうやって国試対策をすればいいのかというと、効果的な勉強法は問題集2周+過去問5年分です。
これについては【看護師国家試験】国試対策いつから始める?絶対受かる勉強法って?で詳しく解説しているので、こちらの記事を参考にしてください。
簡単にまとめるとポイントは以下の通りです。
- 問題集1冊を暗記するつもりで解く
- 答え合わせをして終わりではなく、なぜその答えになるのかきちんと理解する
- プール問題に慣れる
- 過去問を5年分解いて出題傾向を掴む
まとめ:筋道を立てた国試対策で「勝ち」を取ろう
国試に受かった先輩たちが言う「1ヶ月前から勉強を始めて受かった!」、「ぎりぎりでも諦めなかったら大丈夫!」という体験談はとても魅力的ですよね。
なんだか自分にもできそうな気がしてきます。
ただ、こうした体験談は結果論でしかないため、「1ヶ月勉強すれば受かるんだ」と話を鵜呑みにしてしまうのはとても危険です。
ぎりぎりで国試対策を始めて合格した人の真似をしても、自分が同じように合格できるという保証は全くないので、このあたりは上手く判断してほしいと思います。
国試が終わるまで、あるいは国試の結果が出るまでは緊張の日々が続くと思いますが、看護師国家試験はきちんと対策していれば必ず合格できる試験です。
だからこそ、今のうちに勉強に取り掛かって、十分な国試対策の時間を確保してください。
そうすれば必ず合格できますから^^
第104回助産師国家試験:2021年2月11日(木)
第107回保健師国家試験:2021年2月12日(金)
第110回看護師国家試験:2021年2月14日(日)